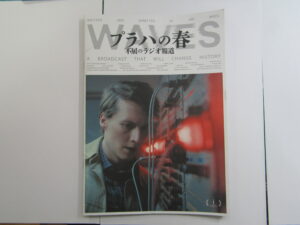歴史の教訓に学ぶ
夏目漱石の書簡集を読んだ。1906(明治39)年10月26日付鈴木三重吉宛に次の一文がある。
「死ぬか生きるか、生命のやりとりをする様な維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい。それでないと何だか難をすてて易につき、劇を厭うて閑に走る、いわゆる腰抜文学者のような気がしてならん」。
この時期、漱石は『吾輩は猫である』を刊行中である(上1905年10月刊、中1906年11月刊、下1907年5月刊)。『猫』を書いていた漱石の思いが、本気だったことがわかる一文だ。その漱石は『猫』の最後で、こんな一文を書いている。
「凡ての大事件の前には必ず小事件が起こるものだ。大事件のみを述べて、小事件を逸するのは古来から歴史家の常に陥る弊竇(ヘイトウと読む)である」と。
この漱石が警鐘を発したわずか18年後の1925年には治安維持法が制定され、日本は戦争の途を突き進むことになる。漱石流にいえば「小さな事件」(但し、治安維持法の制定は決して小さくはないのだが)が「起こ」り、大事件に至ったことになる。
現代日本社会に眼を転じた時、2026年1月23日には意味不明の衆議院解散が行われた。小党分立抗争、国民の政治不信、この行き着く先に一党独裁の国家体制が構築されたことは昭和史の教えるところである。「小事件」を摘み取っておかねばならない。